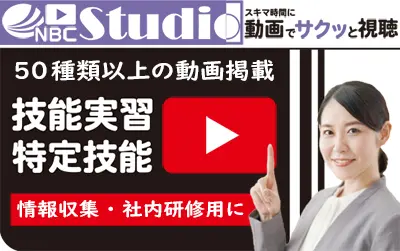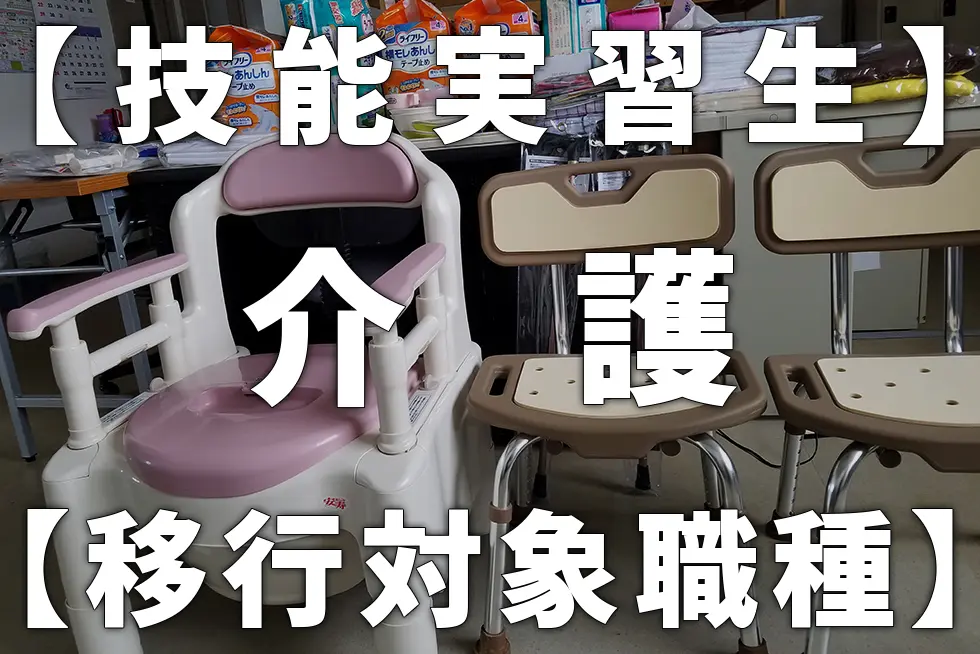
技能実習の移行対象職種のひとつである「介護」職種は2017年に認可職種として追加された比較的新しい職種です。
今回は、介護職種について深堀りしていきます。
01 技能実習「介護職種」
冒頭でお伝えしたとおり、技能実習の2号移行対象職種である「介護」は、2017年に追加された新しい職種です。
他の技能実習の職種同様、交際貢献のために開発途上国の外国人を日本で一定期間に限って受け入れ、OJTを通じて技能を移転するものとなっています。
01-01 日本の社会的背景
高齢化の進む日本では、増えていく要介護高齢者への対応は待ったなしの状態となっています。
団塊の世代が全て75歳以上となり、要介護高齢者が増大するとされている2025年には248万人の介護人材が必要とされていますが、日本は少子化に拍車がかかっており、その2025年には約30万人の介護人材が不足するとの見通しがあります。
01-02 外国人材の受け入れ
「二国間の経済連携の強化」のために、EPA(経済連携協定)に基づき2008年にインドネシア、2009年にはフィリピン、2014年にはベトナムからEPA介護福祉士候補者としての来日がはじまりました。
2017年4月には、更なる活躍促進のために、EPA介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスが追加されました。
2017年9月1日には在留資格「介護」が施行され、同年11月1日に技能実習制度の対象職種として「介護」が追加されました。
そして2019年4月には、労働力として外国人材を受け入れることのできる特定技能が施行され、介護分野での外国人労働者の受け入れがはじまりました。
02 「介護職種」と他の移行対象職種との違い
技能実習制度の2号移行対象職種は、2020年12月現在82職種150作業ありますが、「介護職種」はその実習内容から、実習生に求められる日本語レベルが高くなっています。
02-01 技能実習生に求められるもの ~高い日本語能力
介護職種に携わる技能実習生は、入国段階で日本語能力検定「N4」相当の日本語力が必須条件とされています。
実習をおこなうのが介護の現場のため、日本語でのスムーズなコミュニケーションが求められるからです。
また、介護の現場ということから、高いホスピタリティも併せて求められます。
ミャンマーからの介護技能実習生が多い側面に、ミャンマー語と日本語の文法の相似と、ホスピタリティの高い国民性があるといわれています。
02-02 実習実施者に求められるもの
技能実習生だけでなく、実習生を受け入れる実習実施者にも条件が課せられています。
まず、設立後3年を経過している安定した事業所が対象とされています。
また介護職種といっても、技能実習生の人権擁護と在留管理を適切におこなうために、訪問系の介護サービスは除かれています。
そして、技能実習指導員の要件として、技能実習生5名につき1名以上を専任する必要があり、1名以上は看護師もしくは介護福祉士である必要があるなど、実習実施者にも高い意識が求められます。
03 技能実習以外の介護職種
すでにお伝えしたように、外国人が介護職種に携わるためのビザが技能実習以外にもあります。
03-01 EPA(経済連携協定)
EPAは、2国間の経済活動の連携強化を目指しておこなわれるもので、労働力不足への対応ではありません。
2008年にインドネシアから、2009年にはフィリピンからEPA介護福祉士候補者として来日が開始されました。
2014年にはベトナムからも候補者の入国が始まりましたが、いずれも母国での看護師資格や日本語能力が求められています。
4年間のEPAの期間に介護施設や病院などで特定活動として研修をおこない、介護福祉士の国家試験合格をめざします。
03-02 特定技能「介護」
特定技能の「介護」は、2019年4月1日にはじまりました。
介護の受け入れ見込み数は60,000人でしたが、他の職種同様に出足の鈍さが目立ちました。
ただ、2019年6月には0人だった特定技能外国人が、1年後の2020年6月には170人に増えており、今後も順調に増加していくとみられています。
03-03 在留資格「介護」
2025年には介護人材が248万人必要といわれており、早急な対策がもとめられています。
しかし本邦の少子化により、今後も日本人の介護人材は不足するとみられています。
専門的な技術を要する外国人を介護人材として受け入れるために、2017年9月1日に在留資格「介護」が施行されました。
外国人留学生として介護福祉士養成施設で実習に携わった外国人材、またEPAにより入国し介護の現場で就労・研修をおこなった介護人材が介護福祉士の国家試験を受験し、合格することで晴れて在留資格「介護」を取得することができます。
在留資格「介護」になると、在留期間更新の回数制限がなくなり、また家族の帯同も可能となります。
04 日本の介護現場の悩み
少子高齢化が叫ばれ始めて久しいですが、それ以外にも介護の現場には悩みがあります。
04-01 (日本人の)離職率の高さ
介護の現場での一番の悩みは離職率の高さです。
高齢化が進んでいる日本では介護の現場での人材確保が不可欠ですが、肉体的にも精神的にもハードな現場ということもあり、なかなか定着せず人事担当者が頭を抱えていると聞きます。
場所によっては離職率が3割を超えるという話も耳にします。
あと4年もすれば2025年がやってきますが、必要な人材がなかなか確保できないのが現状のようです。
05 技能実習生が長く在籍するためには
技能実習生は、技能実習1号が1年、技能実習2号が2年、合計3年間の実習を終えると本国へ帰っていきます。
しかし他の技能実習より高いハードルを超えて来日した介護技能実習生です。
より長く在籍する方法はないでしょうか。
05-01 長期在籍への道その1 ~技能実習3号へ
2017年11月1日に改正された新たな技能実習制度により、一定の条件をクリアすることで技能実習3号に移行し、技能実習期間を2年間延長することができるようになりました。
技能実習3号へ移行するためには3つの条件があります。
01 技能実習生が、技能検定随時3級に合格すること
02 実習実施者(受入企業)が技能実習機構より優良認定をうけること
03 監理団体が一般監理事業(優良認定)であること
(☆エヌ・ビー・シー協同組合は一般監理事業です!)
これら3つをクリアしてはじめて技能実習3号への移行が可能となり、トータル5年間の技能実習が行えるようになります。
05-02 長期在籍への道その2 ~特定技能へ
技能実習3号の5年間を終えると、技能実習生としてはこれ以上の在留はできません。
しかし5年間も在籍した技能実習生は、日本人社員に置き換えてみれば、もう立派な中堅社員です。
実習で培った技術力だけでなく、長く在籍したことで社風にも慣れ、人間関係もできあがった技能実習生は、すでに欠くことのできない人材となっていることでしょう。
これまでは帰国するより他はありませんでしたが、2019年4月1日に施行された「特定技能」により、さらに5年間の在留が可能となりました。
特定技能ビザを取得した介護技能実習生は、さらなる活躍をみせてくれるはずです。
05-03 長期在籍への道その3 ~国家資格「介護福祉士」へ
5年間の特定技能1号を終え、次は特定技能2号へと進んでいきたいところですが、現在のところ、在留期限に上限のない特定技能2号(※3年、1年または6ヶ月ごとの更新が必要)には介護職種は含まれていません。
しかし、技能実習1号から特定技能1号まで足掛け10年介護の現場に携わり、技術的にも日本語レベル的にも完全にベテランの域に達している元技能実習生には、国家資格「介護福祉士」の受験のチャンスがあります。
ここで合格すれば、晴れて在留資格「介護」に切り替えることが可能です。
現在のところ、技能実習生の国家試験合格の例はありませんが、特定技能が始まった今、決してありえない話ではありません。
06 まとめ
高齢化社会が進む今、外国人介護職員のいる社会でさまざまな文化が融合し合い、より多様で豊かな地域共生社会の創造と共存共栄をしていくことこそが期待すべき未来なのかもしれません。
そして日本の技能実習で学んだ介護技術は、日本でだけでなく、元技能実習生たちが帰国してからも必ず活かされることでしょう。
介護技能実習をご検討中の企業様、人事採用担当様は、この機会に是非エヌ・ビー・シー協同組合にご相談ください。